連作もの雑感5
『新・平家物語』(1972年)
=メモ=
高橋氏が三度目に出演した大河ドラマ。1963年放送開始の『花の生涯』より数えて10作目となるこの大河(当初は大型時代劇と呼ばれていた)は、吉川英治氏の原作を基に過去9作の大河に出演した俳優の大半をキャスティングした大河史上、“空前絶後”と呼ばれる作品である。
1965年の『太閤記』の織田信長、1969年の『天と地と』で武田信玄を演じた高橋氏も当然ながらお呼びがかかり、源頼朝役で出演。高貴な容貌に氷のようなまなざしの頼朝は、この時代と年恰好の俳優ではやはりこの人をおいてやれそうな人間は考えられず、後半からの出演ながら粋な人選であったようだ。1965年の『太閤記』で秀吉役だった緒形拳氏も阿部麻鳥役で出演。主役の平清盛は仲代達矢氏、平時子は中村玉緒氏、常盤御前は若尾文子氏。その他十七世中村勘三郎氏、新珠三千代氏、佐久間良子氏、初代水谷八重子氏等が出演。ただし、豪華俳優陣を集めた割に作品として「成功」の部類に入るかどうかは中々に微妙(それでも昨今の大河ドラマよりはハイレベル)なようで、それはこの年、札幌冬季オリンピックとミュンヘンオリンピックが開催されたことも無関係ではなさそう。また、プロ野球中継とボーリング中継も裏番組としてぶつけられ、筋書きのないドラマの方に人々の目が向いていた時代だったのだろう(管理人推理)。
再三、触れているがこの作品は総集編と最終回しかNHKに保管されていないと言われている。この雑感も雑感4『天と地と』同様、朝日・毎日・読売の3紙縮刷版から各回の「あらすじ」を可能な限り引用し、「総集編 上ノ巻」「総集編 下ノ巻」それぞれの雑感を記す。
(※あらすじの引用に関しては、敬称略)
〜上ノ巻〜
●第一回
「週刊朝日」に七年間にわたって連載、平清盛に新しい人間像を加えた吉川英治の大作を、平岩弓枝が脚色。
清盛のおい立ちから、保元、平治の乱を経て確固たる地位を築いたかに見えた平家一門が、清盛の死後あわのごとく消えるまでを、清盛を軸に壮大なスケールで描く。第一回は、父忠盛(中村勘三郎)と母泰子(新珠三千代)とのいさかいなどを織込みながら、わが身の出生の秘密を知って動揺する少年時代の清盛を描く。第一回の清盛には、仲代達矢と内田芳郎(少年時代)がふんする。
(1972年1月1日/朝日新聞14面より)
[コメント]
この作品を制作するにあたり、大映京都撮影所から牛車を拝借しているせいだろうか?大映の俳優の起用が目立つ。少年時代の清盛を演じた内田芳郎氏は大映の『ガメラ』シリーズや関根(現:高橋)惠子氏と共演した『高校生ブルース』『新高校生ブルース』、ドラマ『ママはライバル』などで当時お馴染。若尾氏、中村氏の両女優が清盛を軸にしたライバル関係の役に配されている。
●第二回
清盛(内田芳郎)の母、派手好きな泰子(新珠三千代)は忠盛(中村勘三郎)との貧乏暮らしにたえきれず、中御門家に帰った。
三月、都に馬市が立った。清盛は偶然、なつかしそうに近づく母泰子に呼びかけられたが、清盛はかたくなに拒否した。
一方、遊女宿で、清盛に彼の出生の秘密を教えた鳥羽院に仕える武士遠藤盛遠(近藤洋介)は、同僚の源渡(林秀樹)の妻袈裟(三浦真弓)に激しい恋慕の情を打ち明けていた。
(1972年1月9日/朝日新聞13面より)
[コメント]
テレビ欄では勘三郎氏トップ、以下新珠、内田、五十嵐じゅん(現:五十嵐淳子。中村雅俊夫人)、野村万之丞、三浦真弓の各氏が表記されている。民放裏番組を紹介すると、『おれは男だ!』(日テレ)、『72年歌うライバル大激戦』(TBS)、『一心太助』(フジ)、『遠山の金さん捕物帳』(テレ朝)、『日曜ワイド笑』(テレ東)となっている。民放の裏番組も現在、DVD化されたりCSで再放送されている番組ばかり。結構な激戦区だったことがわかる。
●第三回
忠盛(中村勘三郎)の昇殿をめぐり、公卿たちの不満がつのった。彼らにとって、自分たちの番犬ぐらいにしか考えなかった武士との同席はたえられない。だが公卿の中にも忠盛に心をよせる者もいた。
そのころ父の使いで、時信邸を訪れた清盛(仲代達矢)は、時信の娘・時子(中村玉緒)を知った。
(1972年1月16日/朝日新聞11面より)
[コメント]
主演の仲代氏がいよいよ本格的に登場。テレビ欄では仲代氏、水谷八重子氏、中村勘三郎氏、玉緒氏、新珠氏、中村伸郎氏、五十嵐氏、蜷川幸雄氏(まだ俳優やってた頃)、小沢栄太郎氏が掲載されている。
●第四回
清盛の母泰子(新珠三千代)が去ったあと、今出川の邸には有子(水谷八重子)が忠盛(中村勘三郎)の後妻としてはいった。このころ清盛(仲代達矢)は夜ごと藤原時信(下条正巳)の館に通う。娘時子(中村玉緒)とのおう瀬を楽しむためだ。
清盛と時子との結婚披露に多くの人が招かれ、その中に清盛と武者署にに仕える佐藤義清(蜷川幸雄)もいた。いまや古い仲間は義清だけ。久しぶりにくみかわすその席に、事件の報告。義清の部下が源為義(佐々木孝丸)の一党と争いを起した。清盛と源義朝(木村功)との運命的な出あい。
(1972年1月23日/朝日新聞13面より)
[コメント]
テレビ欄だけ読んでいると、蜷川氏が結構重要な役で出演していたのがわかる。別の作品で見た限り、この人はかなり大根だ(笑)。義朝役で往年の名優、故・木村功氏が登場している。
●第五回 3紙ともテレビ欄にあらすじ掲載なし。
●第六回
時子(中村玉緒)は、新築なった広大な六波羅館で、じっと、しあわせをかみしめていた。その日、おじの忠正(浜田寅彦)が新邸を訪れた。新築祝いにことよせて、自分の昇進の口添えを清盛(仲代達矢)に頼みに来たのである。清盛はきっぱりと断った。だが、実はそれ以前、すでに清盛は、藤原信西(小沢栄太郎)に忠正の昇進を願い出ていたのである。うらみがましく帰って行くおじを、清盛は追わなかった。
(1972年2月6日/読売新聞20面より)
[コメント]
ここまで読むと、ずいぶんノンビリした展開が窺える。浜田寅彦氏は『必殺』シリーズなんかの悪い商人役でおなじみ。高橋氏関連でいえば、『風車の浜吉捕物綴 秘剣』で浅利香津代氏が妾奉公に行ってた男、といえばピンとくるだろう。「出世の口添えを頼んで断られる」なんて、TBSあたりで放送されてるホームドラマみたいだ。脚本の平岩氏はTBSで『ありがとう』シリーズや『肝っ玉母さん』なんかを書いた後だろうから、こういう場面はお手のものだっただろう。しかし、その“ホームドラマ”的史観は、当時の視聴者からどう思われていたのだろう?この前年の大河が、萬屋錦之介氏主演の『春の坂道』、その前の年が平幹二朗氏の『樅ノ木は残った』だったことを考えると、路線的にはかなり冒険だったように思えるのだが。
●第七回
院の御所では、近衛天皇の女御代えらびをめぐり、関白忠通(原保美)と左大臣頼長(成田三樹夫)兄弟の間に抜きがたい不信が生じていた。その裏には、鳥羽上皇の寵姫(ちょうき)、美福門院(小山明子)の身勝手と信西入道(小沢栄太郎)の陰謀とがあった。
(1972年2月13日/読売新聞20面より)
[コメント]
総集編では原氏、成田氏の出番はカット。成田氏が出ていたとは驚いた。顔は瓜実型のお公家顔なので、この手の役は確か何度かやっておられる。
●第八回
久安六年三月(一一五〇)、関白忠通(原保美)の養女皇子か、左大臣頼長(成田三樹夫)の養女多子か、帝の后(きさき)の座をめぐっての対立は激しさをました。そんな動きを、信西(小沢栄太郎)はひややかに見つめる。
信西の陰謀は、清盛(仲代達矢)とともに源義朝(木村功)をもその渦中に巻込もうとしていた。
(1972年2月20日/朝日新聞13面より)
[コメント]
同日午後8時より日本テレビ系で『飛び出せ!青春』が放送開始されている。現在のテレビドラマは3ヶ月(約13回)を1クールとして、1月、4月、7月、10月に規則正しく新番組が始まるのが定石らしいが、昔はクールなど関係なく6回とか8回で終わるもの、何年も続くものがあったということを思い出した。
●第九回
清盛(仲代達矢)と義朝(木村功)が愛宕山から持帰った呪符(じゅふ)は、信西(小沢栄太郎)から鳥羽法皇に届けられた。法皇はただちに忠実(森雅之)頼長(成田三樹夫)親子の参内をさしとめた。そのころ何も知らない忠実親子は、近衛帝の死をいたみながらも、皇位継承にからみ、崇徳上皇(田村正和)の皇子小六条の宮を推そうと相談をしていた。
参内さしとめに驚いた二人は身の潔白をたてようと院に急ぐが、参内はかなわない。手をとりあって泣く二人を、信西は冷たく見つめる。一方、清盛は栄達のため手段を選ばぬ公卿からの陰謀にいや気がさしたが、一族郎党の身を思い、じっとがまんする。
(1972年2月27日/朝日新聞13面より)
[コメント]
この日新聞に掲載されている歌謡曲のベスト3は、ニッポン放送では1位:別れの朝(ペドロ&カプリシャス) 2位:終着駅(奥村チヨ) 3位:ちいさな恋(天地真理)。文化放送では 1位:ちいさな恋 2位:愛する人はひとり(尾崎紀世彦) 3位:悪魔がにくい(平田隆夫とセルスターズ)。FM東京では 1位:終着駅 2位:別れの朝 3位:ちいさな恋。文化放送だけチャートの上位3曲中2曲が違っているのがおもしろい。
●第十回
鳥羽法皇の危篤が報じられた日、安楽寿院に向かうおびただしい牛車の群れの中に、ひたすら父・法皇との最後の対面を求めて急ぐ新院・崇徳上皇(田村正和)の車もあった。だがその願いも、信西(小沢栄太郎)らによって封じられてしまった。
法皇の死後、近衛帝呪詛(じゅそ)の汚名を着せられた頼長(成田三樹夫)は、信西らと真っ向から対決しようと決意し、満々たる野望を秘めて、失意の上皇をことばたくみに扇動していた。
(1972年3月5日/読売新聞20面より)
[コメント]
あらすじを読む限り、差し詰め成田氏と小沢氏の権謀術数合戦。日曜8時に濃すぎ、嬉しすぎの展開。
●第十一回
親と子、兄と弟が、互いに敵味方に別れて血を流し合った保元の乱は幕を切って落とされた。天皇方に加わって、手柄などむとんちゃくに、大らかに戦う清盛(仲代達矢)の姿を中心に、同じ天皇方に味方しながらも、父や弟たちと相争わねばならない源義朝(木村功)の苦衷を描く。
(1972年3月12日/読売新聞20面より)
[コメント]
切れ切れに見えるテレビ欄からの情報だと、新聞では仲代氏トップ、以下山崎努→田村正和→木村功→緒形拳→小沢栄太郎の各氏がクレジットされているようだ。同日のテレビ欄の他情報には、午後9時からの『ラブラブショー』では「婚約おめでとう!」特集で渡瀬恒彦氏と大原麗子氏がゲストで登場している紹介文。
●第十二回
保元の乱は後白河天皇方の勝利に終り、敗れた崇徳上皇(田村正和)は、わずかな供を連れて東山へ落ちのびた。そのころ、流れ矢で傷ついた上皇方の藤原頼長(成田三樹夫)は奈良・興福寺にひそむ父忠実(森雅之)を頼って逃げたが、父との対面は許されず路上で死んでいった。
(1972年3月19日/朝日新聞13面より)
[コメント]
武家社会を描く大河ドラマでは、父子の相克を描くのは定石。最近だと1988年の『武田信玄』あたりが最後だろうか。時代の流れに応じて、大河ドラマで取り上げるテーマも変わってきているが、大上段に構えるドラマ枠の割に、矮小化・ホームドラマ化された“陳腐な取り上げ方”が目につくようになってきた。そのような取り上げ方に違和感を持つ向きにも、(民放に時代劇枠が1つしかないので)いまや金曜時代劇しか残されていない。管理人個人としては、伝奇物と歴史物の中間を取った題材なんかをつくってきた水曜時代劇のような枠を復活させてほしい。
さて、新聞テレビ欄の序列だが、仲代→中村玉緒→山崎→緒形→森→木村→伊吹吾郎→藤田まこと→田村→成田の各氏の順。小さなテレビ欄にめいっぱい表示されている。
●第十三回
浮かぬ顔の清盛(仲代達矢)を、戦勝祝いにとみごとなコイをたずさえて伴卜(藤田まこと)が訪れた。だが、信西(小沢栄太郎)への、叔父・忠正(浜田寅彦)親子の助命嘆願も功を奏しなかったいま、清盛は伴卜の意を受ける気にはならなかった。数時間後にはみずから叔父の処刑に立ち会わねばならないのだ。
(1972年3月26日/読売新聞22面より)
[コメント]
裏番組の『一心太助』(杉良太郎氏主演)が最終回。
●第十四回 あらすじ入手できず。
●第十五回
保元の乱の翌年三月、清盛(仲代達矢)は時子(中村玉緒)や頼盛(山本学)とともに、美福門院(小山明子)の主催する花見の宴に招かれていた。広い庭で頼盛は、美福門院やその娘の璋子内親王(荒井麻友子)たちのいる宮殿に迷い込んだ。
(1972年4月9日/読売新聞20面より)
[コメント]
「豆鉄砲」というコラム欄で四月七日より放送開始されてTBS系列の『シークレット部隊』の批評。『ザ・ガードマン』の後番組ということで見る目も厳しかったのか、筋書きが勝手放題のご都合主義と酷評されている。先だってCSのTBSチャンネルで大映ドラマ第1回放送特集の際にこの1回目を視聴したのだが、そんなに悪い出来ではなく、デビュー時の三浦友和氏も初々しかった。全話見てみたい気もする。
●第十六回 3紙ともテレビ欄にあらすじ掲載なし。
●第十七回
舞台は平治の乱へと推移する。保元の乱後、信西(小沢栄太郎)の独裁ぶりや平家一門の繁栄は、右衛門督信頼(亀石征一郎)ら公卿たちや、信西から好意を示されない源義朝(木村功)たちの反感をかもしていた。義朝は出仕もせず常磐(若尾文子)の家に入りびたりの日々。そんな義朝のもとにある日、信頼から密書が届いた。
(1972年4月23日/朝日新聞13面より)
[コメント]
この日からTBS系夜7時半より『ミュンヘンへの道』がスタート。昼の時間帯にはフジ系で『金メダルへのターン』の再放送、テレビ朝日系で『ミュンヘンへ超ウルトラC 体操五輪選考会』という中継。そろそろオリンピック熱が高まってきている。一方、大河の方は、テレビ欄に水谷八重子氏の名前も加わってにぎやかな様相。
●第十八回
平治元年十二月九日の夜半、都の西東から地鳴りに似た人馬の足音が起こった。にくい信西(小沢栄太郎)を討って実権を得ようと、熊野もうでの旅に出た清盛(仲代達矢)の留守をねらって、右衛門督信頼(亀石征一郎)がたくらんだ平治の乱の始まりである。信頼方には源義朝(木村功)を筆頭に、源氏の一門が加担した。
(1972年4月30日/読売新聞20面より)
[コメント]
『ミュンヘンへの道』の裏番組には、『ムーミン』、『ステージ101』など懐かしいラインナップ。
●第十九回
都の変を聞き、急ぎ馬首をめぐらせた清盛(仲代達矢)らは、途中、伊藤武者景嗣(石森武雄)ら、平家ゆかりの武将たちに守られて六波羅に帰った。そのころ宮中では、自ら近衛大将を名乗る信頼(亀石征一郎)が、毎日を酒色に明け暮れていた。清盛は、信頼、義朝(木村功)追討に立ち上がる。
(1972年5月7日/読売新聞20面より)
[コメント]
「馬首をめぐらせる」って絶妙な表現。たった数行の新聞紹介文にも書き手のセンスが表われる。テレビ欄ゆえ、他の番組の紹介文や読者投稿が掲載されているのだが、記者も読者も文章が上手く、論点が硬派。このようなところからも32年前の良識が窺われる。
●第二十回
平重盛(原田大二郎)を総大将とする平家の軍勢は、赤旗をひるがえしながら、皇城に攻めかかった。この日の清盛(仲代達矢)の作戦は、まず重盛を侍賢門から攻めいらせ、戦い半ば、退くとみせて敵を誘い出し、その間げきに乗じて、都芳門から頼盛(山本学)の軍勢がはいり、内裏を占拠せしめることであった。
(1972年5月14日/読売新聞20面より)
[コメント]
皇城に矢を向けている描写が結構はっきり書かれていて驚く。南北朝の争乱を描いた『太平記』の映像化が1991年までできなかったことについては、巷間、いろいろな説が出回っているが、題材は違えども、70年代の大河できわどい描写に挑戦していたのは何となくわかる。それにしても当時の俳優座の人材の豊富さには脱帽(原田氏だけは文学座)。同期生と先輩かき集めれば、名作が出来上がるって感じだ。
●第二十一回
激しさをきわめた平治の合戦に平家は勝った。乱後、平家一門は次々と官位につき、平家の上に春の日が輝き始めた。一方、敗れた源氏こそあわれであった。義朝(木村功)頼朝(岡本清太郎)ら主従六人は、人目を忍びながら、東国へと落ちていった。
(1972年5月21日/読売新聞20面より)
[コメント]
このあたりは総集編でも割合、収録されている。岡村清太郎氏は1969年の『天と地と』の中村光輝氏同様、子役の名演技を見せている。なお同日の夜9時に東芝日曜劇場で吉永小百合・林与一両氏主演の『あだこ』(仲代氏夫人の故・隆巴氏脚本)が放送されているが、こちらも今年、CSのTBSチャンネル枠で何度か再放送されていることを考えれば、NHKの番組保存状況はもう少し何とかならなかったのだろうかと残念である。
●第二十二回
明るくはなやぐ六波羅に、夫の信西の死後も宮中に隠然たる勢力を持つ紀伊局(大塚道子)が訪れた。時子(中村玉緒)の妹の滋子(村松英子)を手もとに置きたいという美福門院からのことづてを持ってきたのだ。ゆくゆくは後白河上皇の側室にしたいという。
(1972年5月28日/読売新聞20面より)
[コメント]
この前の週(5月17日付朝日夕刊7面)に「頭丸めた仲代達矢 滝沢修が“引導”わたす」という記事があった。これによると、後白河法皇役の滝沢氏の方が先に頭をまるめて、「お前もそれ」と進められ、「カツラもかぶってみたんですが、首がよく回らなかったり、先生(滝沢)がそったのだから、つり合い上僕も…」と。剃ったのは渋谷のNHK放送センターの会議室で、共演者の中村氏、中尾氏、原田氏、藤田氏らが集って約三十分で完成。坊主頭で登場したのは七月九日放送分だったようだ。後半の登場人物として、栗原小巻氏や高橋氏、志垣太郎氏、佐藤允氏、林与一氏らの名前が紹介されている。この記事の右側に映画広告が掲載されていて、東宝創立40周年記念作品第1弾『忍ぶ川』の広告。当時の栗原氏の売れっ子ぶりがうかがわれる。
●第二十三回
清盛(仲代達矢)の前に、頼朝(岡村清太郎)をはじめ、常磐(若尾文子)とその三人の子がはじめて姿を見せた。あまりにもいたいけな子どもたちであった。清盛は処置に迷った。むほん人の子だから本来ならば死罪である。清盛はついに、敵将・源義朝の四人の遺児の赦免状を書いた。頼朝は伊豆へ流罪、常盤の三人の子は寺院にあずけられることになった。
(1972年6月4日/読売新聞20面より)
[コメント]
三人揃っての場面は残念なからカットされているものの、清盛に助命嘆願を乞う池禅尼(初代・水谷八重子氏)の場面は総集編にも収録されている。清盛の情緒的な場面ゆえ、きっと2005年の大河『義経』でもこの場面は引っ張ることだろう、と推察する。
●第二十四回
平家一門の台頭ぶりは、だれの目にもきわ立って見えた。都は六波羅景気にわき、町のそこここには清盛(仲代達矢)と常磐(若尾文子)のあらぬうわさも立ち始めていた。そんなある日、清盛は源義朝の遺児・義平(石川徹郎)に襲われ、手傷を負って家臣伊藤景綱(石森武雄)の屋敷に避難するが、そこは子らと別れ、ぬけがらのような毎日を過ごしている常盤の仮の住宅でもあった。
(1972年6月11日/読売新聞20面より)
[コメント]
新聞では触れられていないが、手傷を負った清盛には伴卜(藤田まこと氏)が同行している。『てなもんや〜』が放送終了後、やや低迷期を迎えた藤田氏が再ブレイクするきっかけとなったのは、この大河翌年より放送開始された『必殺仕置人』の中村主水役。『新・平家〜』への出演は、いわば上昇運に乗りかけた時期だったといえよう。『新・平家〜』には必殺シリーズの第1作となった『必殺仕掛人』の梅安役の緒形拳氏、仕置人で共演することになる山崎努氏も出演していて、プレ『必殺』シリーズの様相。
●第二十五回
清盛(仲代達矢)が襲われたという知らせに、六波羅館には武装した者たちがつめかけた。義平(石川徹郎)らふたりの源平残党に襲われて景綱(石森武雄)の屋敷に逃げ込んだとあって、いささか間が悪い。時忠(山崎努)や忠度(中尾彬)ら弟たちは、清盛の気ままな外出を非難した。そのうえ、時子(中村玉緒)からは、傷に巻かれた白布の移り香をとがめられ、今後二度と常盤(若尾文子)とだけは会わないでくれと、涙ながらに訴えられた。
(1972年6月18日/読売新聞22面より)
[コメント]
勝新の生前には、いろんなスキャンダルに悩まされて「すんまへん」と謝り通しだった中村氏も、近年ではかなりバラエティー化して勝新ネタや借金ネタで笑わせるようになってきた。女は怖し(笑)。
●第二十六回
明け方近く、清盛(仲代達矢)を襲った悪源太義平(石川徹郎)と金王丸(平野康)が、六波羅の手勢にとりかこまれたところ、清盛邸の庭先では、老臣の木工助家貞(高桐真)が、卒中の発作に倒れ、清盛の腕にいだかれて息を引きとろうとしていた。
(1972年6月25日/読売新聞20面より)
[コメント]
久々に裏番組を紹介すると、テレ朝系では中村梅之助氏主演の『遠山の金さん捕物帳』。金さんが人足に化けて潜入したストーリー。テレ朝系のこの日のラインナップを見ていたら、いとこい師匠の『がっちり買いまショー』(3万円、5万円、10万円…でおなじみ)と小池清氏司会の『アップダウンクイズ』が。毎日放送と朝日放送のネット交換が行われるのは、翌1973年のことである。
●第二十七回
“上の巻”を終了する今回は清盛(仲代達矢)と常盤(若尾文子)の別れを中心に描く。
(1972年7月2日/毎日新聞20面より)
[コメント]
札幌オリンピックが終わって5ヶ月あまり経つというのに、フジテレビでは同じ時間帯に高橋圭三氏司会で『緊急特集!ジャネット・リンのすべて』という1時間番組を放送。夏季大会のミュンヘンを盛り上げる意図ももちろんあったのだろうが、当時の彼女の人気ぶりもうかがえる。
|
総集編 |
題名 |
上ノ巻 |
| 感 想 |
全52回の放送分をのうち、前半27回分を1時間半に再編集した「上ノ巻」。この1時間半のエッセンスだけで判断したベストアクターは先代中村勘三郎氏に進呈したい。私にとって、「勘三郎」という名前がしっくりくるのはやはりこの人であり、今度襲名する勘九郎氏には申し訳ないが、やっぱり違和感がある。
本作の小道具として度々登場する梅の花。冒頭、これを妻である祇園女御(新珠三千代氏)と愛で、一節うなる小粋な感じとか、なさぬ仲である清盛を惣領としてかわいがり、出生の秘密を知った清盛が、離縁して家を出ようとする母を殴った際の慈愛に満ちた表情、臨終に際しての和解など、少ないながらも場面をさらっていた。
成人後の清盛を演じている仲代氏も当時は40歳くらいだろう。若々しさを表しつつ、単なる貴族の警護役に過ぎない武士団を新たな勢力にしようと奮闘する様子、比叡山の坊主らが守っている神輿に矢を放つ様などは、今のザ・演劇界然とした仲代氏とは全く異なった感じで懐かしい(名優と呼ばれる人たちにありがちなんだけど、どうも収まり過ぎちゃって冒険心が薄れちゃう。年取っても若手と遊べる雰囲気を残してる俳優は、原田芳雄・石橋蓮司両氏くらいではないだろうか)。
この作品、与えられた役がその人にとって“水を得た魚”になったか、“ひからびたクサヤ”になったかで明暗がきっちり分かれてしまった。僭越ながら“クサヤ”系になってしまったのが、森雅之氏。この方、すごく好きな俳優ですし、生前はものすごくモテたともっぱらの噂なんですけど、総集編のカット具合が悪かったのか、それとも脚本が個性を引き出しきれなかったのか、ちょっと残念だった。画面を見ながら(自分の思い描いていた森雅之イメージとは違う。こんなはずでは…)とガッカリしまして、口直しに別な映画を観たくなってしまった。
逆に“魚”系の方は、冒頭に挙げた勘三郎氏と信西入道役の小沢栄太郎氏、頼長役の成田三樹夫氏(コメント欄で総集編に出番はないと書いてたらありました)。小沢氏の入道は、ロシアのラスプーチンの700年早い姿のようだったし、この人が得意とする大番頭系のポジションをがっちりキープ!総集編でこの人が見られるだけでも「買い」だと思う。成田氏も同様。田村正和氏扮する崇徳上皇(前半の悲劇の美男子)に言葉巧みに接近、挙兵させるも失敗して首に矢が刺さった時の悶絶シーンは鳥肌ものだ。ほぼ同世代だとやはり早世した岸田森氏が怪優の名を欲しいままにしているが、岸田氏が東の怪優なら成田氏は西の怪優と呼んでしまいたい。
ちょっと残念なことは、脇役に至るまで超豪華キャストのせいか、出演者それぞれの見せ場を出すために場面を細かく編集してナレーションを被せなければならない。そうすると、話が細切れすぎてかえってストーリーをわかりにくくしてしまっている。また、合戦シーンがすべてセット撮影で行われているせいか迫力にやや乏しい。翌1973年の『国盗り物語』の総集編を見ていただいてもわかるが、合戦シーンを野外で撮った場合、そのシーンだけはフィルム撮影で、室内シーンはVTR。これをつなぎ合わせた総集編を見ると、ちょっと滑稽に見えないこともないが、その時代の精一杯の技術だからその辺は割り切って見ていただくとして、やはりちぐはぐでも合戦シーンは野外ロケにしていただきたかった。どう考えても、豪華キャストの分、野外ロケ予算を切り詰めたとしか思えない。ちなみに、この野外と室内のちぐはぐが解消され、野外でもVTR撮影が可能になった大河というのは、1978年の『黄金の日日』のフィリピンロケからだった。
女優陣では、『氷点』以降イビリ役も引き受けるようになった新珠氏に目が向いた。白河上皇から忠盛に下げ渡されて清盛を産み、その後も子供たちに恵まれるも妻にも母にもなりきれず、女としての業の深さを垣間見せている。臨終間際の忠盛に面会し、息子清盛と久々に再会した場面は、新珠・仲代氏が同じ画面に映る。その数年前、映画『人間の條件』で夫婦役を演じていた二人が今度は親子役で共演。女優も大変だ(笑)。仲代氏はこのドラマ後半には映画『旅路』で夫婦役をやった佐久間良子氏と親子を演じていて、何かすごい状態になっている(笑)。
放送当時、平岩氏の脚本は“ホームドラマ大河”と揶揄されたようだが、清盛を取り巻く女性達−祇園女御、時子(中村玉緒氏)、常盤御前(若尾文子氏)を眺めていると、彼の根底にあるのは「母の愛を渇望する男」の姿であり、これは『源氏物語』の光源氏の女性遍歴にも見られる傾向であるため、むしろ古典的手法ではないだろうか。
この時代(小説も含めて)の表現で、目新しいといえる手法は、「庶民から見た〜」にある。庶民から見た戦後とか昭和史と同義で、本作品では麻鳥役の緒形拳氏がこれに当たる。召し人の麻鳥が流刑されている崇徳上皇に会いに行き、笛でなぐさめる場面は、『黄金の日日』で処刑前夜の千利休(鶴田浩二氏)を助左(現:松本幸四郎氏)が琵琶だかバンジョーだか爪弾いてなぐさめる場面など、その後の大河には何度となく登場する“お約束”。麻鳥の登場する意味はあるのかと考えてみたものの、物語としてどうこうというより、NHK大河第10作記念作品として、『太閤記』の緒形氏が必要なのだと考えれば納得もいく(吉川氏の原作ではどの位の比重なのだろうか)。
小道具としてキーになる梅の花を基調として、池禅尼(初代:水谷八重子氏)が少年・源頼朝(岡村清太郎氏)の助命嘆願。ここで唯一清盛が見せた“スキ”が平家一門の命取りとなる。今度の大河では、『新・平家』にも登場した南風洋子氏が禅尼役をやられるそうだが、これを清盛の慈愛として見せてしまっては間違いである(と管理人は思う)。本作における清盛と弟たちの会話を聞いていると、育ての親である禅尼への気遣いの上で命を助けたものの、「自分の身に何かあった時は…」とちゃんと念押ししているし、清盛の態度を見ていると、平家一門のファミリー企業性、結束の固さに絶対の自信を持っているからこそ、自分の処断後のケアも万全にできるに決まっているとタカを括った上での減刑であることがはっきりわかる。これ、ワンマン経営者によくあることで、決して清盛の慈愛ではないのだ。
奇しくも同じ年、映画『ゴッド・ファーザー』が公開されている。「恩には恩を、裏切りには復讐を」という強烈なキャッチコピーと、妹の夫にも制裁を加える恐ろしさがありながら、どうにも抗えない血の遺伝、哀切さが素晴らしかった。仲代氏の演じた清盛がビトー・コルレオーネ(マーロン・ブランド氏)だとすれば、平家一門にはマイケル・コルレオーネ(アル・パチーノ氏)にあたる人がいなかったということだろう。
平家一門の落日については、下ノ巻雑感で引き続き書いてみたい。 |
〜下ノ巻〜
●第一回
今回から「下の巻」。時代は嘉応二年(一一七〇年)、清盛五十三歳の春。すでに太政大臣に任ぜられ、一門は衰亡の藤原氏に代って要職を占めている。清盛(仲代達矢)は入道姿。建礼門院徳子(佐久間良子)、北条政子(栗原小巻)、源頼朝(高橋幸治)、義経(志垣太郎)、弁慶(佐藤允)、義仲(林与一)らが新登場する。第一回は、成長した徳子、大橋田の浦の築港に力をそそぐ清盛、そして鞍馬で母を恋う牛若丸、源氏の残党金王丸(平野康)、奥州の商人吉次(日下武史)が牛若丸を訪れる。歴史は変わりつつあった。
(1972年7月9日/朝日新聞13面より)
[コメント]
別新聞(掲載紙は忘れました)でみた情報によれば、義経役の志垣太郎氏は当時20歳。デビューが『巨人の星』の舞台版!この前年に『おれは男だ!』で森田健作氏のライバル役で高校生のくせにスナック経営して車を運転していた(笑)。この6年後にはアニメ『ベルサイユのばら』のアンドレの声をあて、エンディングの『愛の光と影』の名セリフを残す。
ある意味、王道を行った(行き過ぎて周りが引いちゃった時もある)二枚目だった。
●第二回
摂政藤原基房と重盛の子資盛との車争いの一件を福原の別荘できいた清盛(仲代達矢)はあわただしく京へ帰る。大輪田築港へ国の補助を仰ぐ大切な時期だ。車争いは摂政家をおこらせ、後白河法皇(滝沢修)に再び認可を遅らせる口実となったようである。一方、鞍馬の牛若丸(志垣太郎)の母常盤(若尾文子)は再婚した藤原長成に先立たれ、屋敷は荒れほうだい。病気だとのうわさ、医師麻鳥(緒形拳)、○子(文字不明/和泉雅子)が訪ねる。常磐は病気ではなかった。牛若丸の周囲に焦る源氏残党の動きを知るにつれ、牛若丸の身の安全のために、いっさいの交渉を断つための仮病だった。
そのころ、清盛の命を受けて朱鼻伴卜(藤田まこと)は、奥州の商人吉次(日下武史)の身辺をさぐっていた。
(1972年7月16日/朝日新聞13面より)
[コメント]
「車争い」といえば、『源氏物語』の葵祭りの場面でも、光源氏の正妻・葵の上と愛人・六条御息所が争い、敗れた悔しさから御息所が生霊になってしまう場面があった。平安・鎌倉期の宮中争いを描くには、車を主題とするのが流行っていたのだろうか?今なら何だろう?
●第三回 3紙ともテレビ欄にあらすじ掲載なし。
[コメント]
ただし、7月23日読売新聞20面「てれび街」には、牛若丸(志垣太郎氏)と弁慶(佐藤允氏)の五条大橋の対決シーンの撮影風景について、写真入りで紹介されている。660平方メートルのスタジオに、製作日数4日をかけて五条大橋のセットをしつらえ、牛若丸役の志垣氏をピアノ線で吊り上げた。さらに、撮影には報道用の小型ハンディカメラを使ったことまで書かれている。
●第四回〜第七回 3紙ともテレビ欄にあらすじ掲載なし。
●第八回
治承元年六月、中宮・徳子は病気のため宮中を下がり、西八条へ戻った。京の人々は、平家全盛をぬたむ者ののろいという。
清盛(仲代達矢)は、時忠(山崎努)の屋敷に監禁されている義経を「切れ」という。時忠は弁慶(佐藤允)に命じ、五条大橋で−。
(1972年8月27日/朝日新聞20面より)
[コメント]
上で説明した五条大橋のシーンはこの回。1ヶ月前から取材させるとは、当時のNHKも中々に宣伝上手。
●第九回
後白河法皇(滝沢修)を中心に進められた平家打倒の陰謀は、多田行綱の密訴から清盛(仲代達矢)に知れてしまった。いわゆる鹿ケ谷の陰謀事件である。法皇を除き、一味は平家によって次々に捕らえられ、西光(内田稔)は打ち首に、大納言成親(岡村春彦)、その子成経(高田裕史)、僧俊寛(大塚国夫)、平康頼らは流罪に処せられた。
(1972年9月3日/読売新聞22面より)
[コメント]
ミュンヘン五輪編成か放送時間も夜8:45からとなっていた。
●第十回
北条時政(加東大介)は六波羅での任務を終えて伊豆へ帰る途中で、平家の目代・山木判官兼隆(辻万長)から、娘・政子(栗原小巻)との結婚を申し込まれ承知した。しかし、妹・政子と頼朝(高橋幸治)との恋を見守ってきた嫡男・宗時(鈴木智)は、時政にそのことを話し、政子の心をくんでやってくれと頼む。
(1972年9月10日/読売新聞22面より)
[コメント]
後半に入り、いよいよ高橋頼朝の出番になってきたのがこの回なのでしょう。
●第十一回
山木判官兼隆(辻万長)と政子(栗原小巻)の婚姻の儀式が始まろうとしたとき、山木の館は炎につつまれた。その騒ぎの中で、政子の姿がいずくともなく消えた。何者の仕業ともわからないが、実は源氏にゆかりの者たちのたくらみであり、政子の兄宗時(鈴木智)もその中の一人。激怒した兼隆は頼朝を疑い、配所を見張るが、頼朝の日常は変化を見せない。政子の父時政(加東大介)を責めても時政は平身低頭するだけ。
(1972年9月17日/朝日新聞24面より)
[コメント]
総集編には残されていない頼朝エピソードで一番惜しいもの。この時代にはめずらしい駆け落ち結婚だということはつとに知られておりますが、この演出は1979年の『草燃える』と見比べてみたかった。
●第十二回
治承二年十一月十二日の明け方、中宮徳子(佐久間良子)は玉のような男子を出産した。のちの安徳天皇である。中宮の安産を聞いた清盛(仲代達矢)の喜びは一通りでなく、肩をふるわせて泣くさまは、世の常の親の姿であった。だがそれとは逆に、重盛(原田大二郎)の健康は日々に衰え、夏の夜明け、四十二歳をもって父清盛に先立った。
(1972年9月24日/読売新聞24面より)
[コメント]
ホームドラマ大河と当時は酷評された(らしい)本大河、紹介記事からその片鱗が窺える。ただし作品水準は現在の比ではありません。
●第十三回
治承三年の秋の夜、後白河法皇(滝沢修)の院の御所では、法皇と源三位頼政との間で、またも平家打倒の密議がかわされていた。法皇の第二子、以仁王(北大路欣也)を奉じて事をはかろうというものである。福原でこのことを知った清盛(仲代達矢)は、ただちに武者をそろえ京を目指した。
(1972年10月1日/読売新聞24面より)
[コメント]
同日夜9時半より、フジテレビ系列で若林豪・浜畑賢吉両氏が出演の『おやこ鷹』が放送開始。番組批評欄には「若林の父、浜畑の息子役というのがどうもそぐわない。(中略)実年齢で二歳しか違わないのだから、当然といえば当然なことである」と。50歳過ぎた俳優が信長を演じたり、濃姫よりお市の方がはるかに年上で貫禄ありそうに見えたり、某民放で数年前に放送された作品では、信長の義弟役で信長役よりはるかに年上な北大路氏が浅井長政だったり、最近はもっとひどい(笑)。それを納得させるような演技力や演出はあるのかということはコメントを差し控えたい。
ついでに。『おやこ鷹』の前の番組は『ラブラブショー』で、「壮烈!愛のタッグマッチ! 倍賞美津子ほか」と書いてあるので、多分見合い相手はのちのご亭主になられたアントニオ猪木氏だろう。
●第十四回
関白太政大臣以下すべての官職が解かれ、それらの人にかわって、平家一門が新しく官職についた、そして、後白河法皇(滝沢修)は鳥羽の北殿に閉ざされた。
都のできごとは以仁王(北大路欣也)や源三位頼政(芦田伸介)らのひそやかな動きとともに、金売り吉次(日下武史)によって、奥州平泉の藤原秀衡(加藤嘉)のもとに、つぶさに報告される。源義経(志垣太郎)をかくまっている秀衡は、吉次の報告に興味深げにうなずいた。
(1972年10月8日/読売新聞より)
[コメント]
クーデターの回。この辺は総集編では非常にわかりづらい。記憶違いでなければ、加藤嘉氏の出演場面はカットされていたように思う。もう少し長く入れてほしかった。
●第十五回
平家追討の計略は、思わぬところから清盛(仲代達矢)の耳に入った。六波羅勢が三条高倉御所へ押し寄せたころ、以仁王(北大路欣也)は、いち早く難を逃れて三井寺へ。
(1972年10月15日/読売新聞より)
[コメント]
仲代−北大路のお二人、のちに『華麗なる一族』『不毛地帯』なんかで共演。あらためて考えると、何か変な感じである(笑)。
●第十六回
六月の炎天下、伊豆、蛭ヶ小島の頼朝(高橋幸治)の配所に、戦いに敗れて死んだ以仁王の「平家追討」の令旨が届いた。政子(栗原小巻)の兄北条宗時(鈴木智)は父の時政(加東大介)に頼朝への助力をすすめるが、時政はいっこうに腰をあげない。頼朝は時政の参陣をまたず挙兵。
一方、福原は、急の遷都にごった返し、公家たちの不満は高まる。そんななかで、幼い安徳天皇(山崎有右)は、清盛(仲代達矢)を一日も離せぬ日々だった。
(1972年10月22日/朝日新聞24面より)
[コメント]
テレビ欄には、仲代→山崎努→佐久間良子→高橋幸治→栗原小巻→藤田まこと→真屋順子の各氏の名前が掲載。
●第十七回
ついに源氏旗あげの日がきた。八月十七日の夕刻、頼朝(高橋幸治)方についた北条時政(加東大介)を先頭に、まず、平家の目代、山本兼通(辻万長)の館を攻め落し、三島明神へ向う。明神の森で、一人の武者が現れた。亡き源三位頼政の孫有綱(山本学)である。有綱は頼朝に三島国庁のカギを渡す。開かれた倉には、頼政がこの日を期し、たくわえた多数の武器、糧食、軍用金があった。
頼朝挙兵と北条時政の寝返りは、福原にいる清盛(仲代達矢)にとっては寝耳に水の驚きであった。一方、奥州平泉にいる義経(志垣太郎)は兄頼朝の旗あげを知り、藤原秀衡に別れを告げる。
そのころ、頼朝はすでに石垣山の合戦にやぶれ、ある洞穴(どうけつ)にひっそりと身をかくしていた−。
(1972年10月29日/朝日新聞24面より)
[コメント]
こら、NHKは何でこんなおもしろ回をまるごとカットした総集編を制作したのだ!その上にオリジナルは消去したから二度と観ることはできない。新聞欄の順番(トップ仲代氏、二番手高橋氏。以下、栗原→加東→志垣→緒形→和泉→加藤嘉→中村勘三郎の各氏)から察するに、清盛VS頼朝だったことは明白。
●第十八回
石橋山の敗戦から二か月もたたぬ治承四年十月六日、頼朝(高橋幸治)は、東国の軍勢を結集して鎌倉へ入った。そのころ頼追討の命を受けた平家は、総勢一万の大軍で東へ向かっていた。十月二十日、源平両軍は、富士川をはさんで対し、不意をつかれた平家軍は、朝もやの中に敗れ去る。
(1972年11月5日/読売新聞20面より)
[コメント]
この回も文章から想像するしかありません。
●第十九回
奈良に平家軍が攻め込んだ夜、民家から出た火が東大寺に移り、興福寺を焼いた。いわゆる南都炎上事件である。清盛(仲代達矢)は、重衡(長澄修)らの言い訳めいた報告をきびしくとがめ、太平の世を取り戻すために一門が結束せよとさとすが、そのころ、平家打倒の大きな力が信濃にも起こっていた。
(1972年11月12日/読売新聞11面より)
[コメント]
どうでもいい話だが、同日昼1時5分から放送の『中学生日記』は「ラブレター騒ぎ」。そして同日大河の裏番組『飛び出せ!青春』も片桐君(剛達人氏)が真樹(青木英美氏)に渡す英文ラブレターを河野先生(村野武範氏)に書かせたことが元で起こる騒動「あなたがいなくなると私は淋しい」の回。まだこのころは中高生もラブレターくらいで騒ぎになるかわいい時代だった。
●第二十回
熱病におかされた清盛(仲代達矢)の病状は、時子(中村玉緒)らの看病にもかかわらず悪化する一方。治承五年春、清盛はわが胸に一門を抱きかかえるかのように両腕をひろげ、目を見開いたまま、波乱に満ちた六十四年の生涯を終えた。
一方、頼朝(高橋幸治)が館を備えた鎌倉は、日ごとににぎわいを増す。
(1972年11月19日/朝日新聞24面より)
[コメント]
この場面については総集編雑感に述べます。
●第二十一回
平家の衰退はおおうべくもない。荒波のごとく攻め寄せる木曾の軍勢に、平家は撤退を繰り返す。一方、後白河法皇(滝沢修)は、巧みに平家の内部かく乱をおこす。寿永二年七月、平家はついに都落ちを決意する。
(1972年11月26日/読売新聞11面より)
[コメント]
新聞欄トップは中村玉緒氏、以後、山崎努→佐久間良子→滝沢修→藤田まこと→宮口精二→山本学→中尾彬の各氏。
●第二十二回
平家都落ちの三日後、義仲(林与一)は、巴(古城都)と念願の都入りをする。だが、一足先に行家(織本順吉)が五条に陣を張っていた。二人の間がしっくりしていないとみた後白河法皇(滝沢修)は、二人の離反を策す。
(1972年12月3日/読売新聞より)
●第二十三回 
院の御所を襲撃した義仲(林与一)は、後白河法皇(滝沢修)を押し込め、征夷大将軍になって独裁体制を敷いた。だが、そのころすでに義仲追討の院宣を受けた鎌倉軍は、範頼、義経(志垣太郎)を将に、宇治川に迫っていた。
(1972年12月10日/読売新聞11面より)
[コメント]
新聞欄には中村→山崎→滝沢→佐久間→林→古城→志垣→佐藤允→緒形の各氏。高橋氏の出演はなかった模様。
●第二十四回 
寿永三年二月七日の明け方、義経(志垣太郎)を将とする源氏の軍勢は、(印刷不鮮明)に立つ。眼下の一の谷の平家軍は深い眠りの中にある。不意を襲われて平家の軍勢は混乱し、陣舎は火を吹く。死闘がくりひろげられ、ひとつ、ひとつ、平家の公達の命が散ってゆく。忠度(中尾彬)は敵にかこまれ憤死、敦盛(中村勘九郎)も熊谷次郎直実(岡田英次)との一騎打ちで短い生涯を終えた。勇将知盛(松山省二)は安徳帝の身を案じ、隠れて御座船の守りへ−。
(1972年12月17日/朝日新聞24面より)
●第二十五回(最終回) 
寿永四年三月二十四日、平家は瀬戸内から玄界灘へ抜ける特殊な潮流を利用して、一気に勝敗を決すべく壇ノ浦に排水の陣を敷く。その夜明け、平家は和布刈神社に戦勝を祈願し、軍儀を開いた。
だが、一門にとって最後の軍儀ともいうべきこの席に、長老時忠(山崎努)の姿はない。鎌倉との和ぼく計画の破たん以後、平家一門の彼に対する信用はすでになく、時忠はこのとき、義経(志垣太郎)の軍船の船底にとじ込められていたのである。
別室では、やがて来るであろう最期の時を前に、故清盛の妻時子(中村玉緒)と娘徳子(後の建礼門院=佐久間良子)のしみじみとした語らいが続いた。
(1972年12月24日/朝日新聞20面より)
[コメント]
最終2話で一の谷の合戦と壇ノ浦の合戦を描いている。かなり大変な展開。
 |
総集編 |
題名 |
下ノ巻 |
| 感 想 |
全52回の放送分をのうち、後半27回分を1時間半に再編集した「下ノ巻」。前巻より10年の歳月が流れた設定。この後新進俳優として映画やテレビに引っ張り凧となる西田敏行氏が初めて出演した大河作品で、下巻に登場したことも記しておく。
10年の歳月が経過、世は平家の栄華である。原田大二郎・勝呂誉・古谷一行氏らそうそうたる平家メンバーと、院の勢力が対立しているところから、物語は始まる。
しかしながら清盛の娘、徳子の受内の話は粛々と進められていく。上ノ巻で清盛(仲代氏)と徳子(佐久間氏)の釣り合わない年齢について触れた。この下巻でも高倉帝(片岡孝夫氏)と徳子のシーンはつり合わないことこの上ない(笑)。豪華キャストで彩りを添えることと同じ位、女優の若メイクと老メイクの落差位はなんとか考えられなかったのだろうか。そういう欠点を除けば、清盛と徳子の情愛仕立てにされた別れのシーン、清盛が霙を掌で受け止めるのは印象的だった。
他には鹿ケ谷事件での以仁王(北大路欣也氏)の介錯シーンも捨てがたく、『仁義なき戦い 広島死闘篇』を見ているよう。さらに牛若丸と常盤御前の再会は、源氏の情愛風景として刻み込まれる。
こういった場面と常に対極、ほとんど音楽なしで展開されるのが氷のような頼朝(高橋氏)と政子(栗原小巻氏)の新劇コンビの芝居。この二人のシーンは、源平合戦を横に置き、新劇俳優同士の演技合戦、口跡合戦のようだった。さらに、老獪な後白河法皇に挑む剃刀のような清盛も、腹の探り合いが素晴らしい。目・眉・鼻・唇・指の動きを逃すまいとして画面に集中する。画面を巻き戻す動作でさえ、“物音”として失礼に当るのではないかと緊張してしまう程である。そういえば、テレビを見て緊張する、手に汗握る経験が、子供の頃は週に2〜3回あった記憶がある。ただの娯楽でものすごく贅沢なものを見せてもらってありがとう!と言いたくなる様な幸せな時代だった。
ここで泣かせて、ハイ主題歌かけて、予告篇。視聴率が悪ければ土曜日に総集編放送。番宣がらみでうちのバラエティー番組にも出てね、というパターンが出来上がっている昨今、俳優同士の演技合戦はめずらしい。この映像を見直していると、今ほど臭味のない藤田まこと氏や中尾彬氏がたくさん出てくる。
さて、ここまで盛り上がってきて訪れた清盛臨終のシーン。名場面ではあるものの、臨終までがちと長すぎた。ある本によれば氷もすぐに溶けるような熱病にうかされた清盛なのに、一門が集まる前で立ち上がり、手をかざすまでの体力が果たしてあっただろうか。「竜の爪を研がしむなかれ」はよかったけれど、あの場面が引っ張りすぎだったのが残念。このドラマ「死」をどのように描くかに力点が置かれているが、一番余韻があったのは、敦盛が首を切る際、琵琶の弦が切れる場面を挿入したところだった(ついでにいうと、義仲と巴御前のシーンで見せ場を作った後、頭に矢の刺さる義仲の場面がすぐに挿入されていたが(総集編だから)、あの場面ももう少し別な挿入を入れるともっとよかった)。
高橋氏ファンとしては、政子を結婚式からさらっていく場面が消失しているのは非常に残念だが、総集編下巻にも見せ場はちゃんとあり、命乞いにきた池殿(山本学氏)に対して、表向き温情を与える素振りを見せながら、「恩を施したとて恨みは恨み。政に情は無用」とつぶやき、高笑いを浮かべるシーンは必見。台詞回しは単調に見えるが、目の動きや抑揚によって芝居の落差はちゃんとあるし、なんと言ってもあの高笑いは訓練された新劇役者にしかできません。
それ以降、壇ノ浦へと一気に見せてくれるわけですが、沈んでいく陽と凪いでいる海の映像がさりげなく挿入されていたシーン、出家して建礼門院となった徳子と後白河法皇の場面はツボでした。
|
(了)
※姫君のイラストは 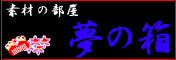 から拝借しております。
から拝借しております。
連作もの雑感目次へ
