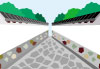今や文学において「純文学」「大衆文学」とジャンル分けすることはナンセンスだと笑われてしまう。大衆文学の中に入るミステリーが芥川賞や直木賞を受賞することが多くなってきたのがその一因だ。しかし、ミステリーだって厳密に言えばハードボイルドと分けて考えなければならないはずだ。まあそう硬いこたぁ言わずに素直に楽しめばいいと言われればそれまでなのだけれど、「純文学者が書いたミステリー」と「大衆作家が書いた純文学」には、優劣の差はないが味わいの違いはあってほしいと思う。
今や文学において「純文学」「大衆文学」とジャンル分けすることはナンセンスだと笑われてしまう。大衆文学の中に入るミステリーが芥川賞や直木賞を受賞することが多くなってきたのがその一因だ。しかし、ミステリーだって厳密に言えばハードボイルドと分けて考えなければならないはずだ。まあそう硬いこたぁ言わずに素直に楽しめばいいと言われればそれまでなのだけれど、「純文学者が書いたミステリー」と「大衆作家が書いた純文学」には、優劣の差はないが味わいの違いはあってほしいと思う。国民的作家として故・司馬遼太郎氏と共に戦後日本文学を牽引してきた故・井上靖氏は、純文学者としてのミステリーを『崖』『氷壁』などで著した数少ない作家と言える。
御茶ノ水駅付近にある大学病院に、ある晩男が搬送されてくる。頭部裂傷の上、意識を回復したときには記憶の一部を喪失していた。男が覚えていたのは山代大五という自分の名前と生年月日と新聞記者をやっていること。しかし年齢や今日の日付を思い出すことができない。山代は逆行性健忘症にかかり、三年前からの記憶がすっぽり抜け落ちた状態になっていた。その三年の間に新聞社も退職、係累もない山代の記憶回復には相当の時間がかかると医師団が覚悟していた頃、香村つかさと名乗る女性が現われ、山代は画廊を経営していて自分はそこの社員であると証言する。
つかさの協力を得ながら、山代が喪失した三年間の記憶を取り戻していくことが本作の「核」である。失われた記憶という漠然としたものを追い、そのためには山代の長所・短所、過去が容赦なく暴かれていく。通常の人間は、都合の悪い記憶は抹消してしまう能力があるが、病み上がりの身である山代には勿論、その能力は働かない。都合の良し悪しに関らず、何かの拍子に断片的なものが浮かんでは消えていく。そして一つの疑惑(セザンヌの贋作売りつけ)と一人の女性(八束陽子)が山代の心を次第に占めていくようになる。
同時にこの物語は、山代の新たな人格形成と恋の物語でもある。山代の過去への水先案内人である香村つかさの接し方がおもしろい。雇用者(山代)と使用人(つかさ)の関係は、山代が記憶を失った時点で逆転する。よるべなき山代を子供をあやす母親のように世話し、ゆかりある地に根気よく連れ出す。健全なる奉仕の精神とも言い切れず、おもしろがっている風でもない。欠落した記憶のブランクを埋めつつ、新しい山代をつくり、新しい山代が過去の山代を第三者的視点で客観的に評価できるようにしようと奮闘している。そのプロセスを踏みながらつかさと山代は当然ながら恋に落ちていくのだが、記憶を回復した時点で自分への気持ちも消滅するのではないか?という複雑な思いを抱えてもいる。
その点、管理人も「主人公は昔の恋人に会った途端、愛の力で記憶を回復、三角関係が展開するのか」と興味深く読み進めていた。
現在の山代はその女性に会いたいとも、その女性と話をしたいとも思わなかった。失われた過去三年の間における彼女との交渉が、どのようなものであるかということは心配であり、そのために彼女のことを繁く思い出しては来たが、それは彼女に対する思慕の念とは違っていた。はっきり言うと、山代の自分の心の中に、曾て彼が持っていた思慕の念がすっかり死滅していることを知らなければならなかった。
それならば、あれだけ烈しかった恋情はどこへ行ってしまったのであろうか。そのような変化はどのようにして、いかなる理由で行われたのであろうか。
外見上は恵まれた体躯を持っていて頭脳明晰。一線の新聞記者として活躍していた山代が、家庭教師として教えていた令嬢・陽子への秘めたる愛を持ち続ける姿は、哀れを通り越してやや滑稽にさえ見える。恋の主導権は常に陽子の側にあり、山代は気位の高い陽子に翻弄され続ける。つかさと共にあらたな自分を構築しつつも、告白一つするにも(過去にこのようなことがあったのでは)といちいち思いめぐらせ、その度に浮かび上がる陽子の記憶。そしてもう一人浮かび上がる女性の記憶。過去の女性二人の記憶がセザンヌの贋作売りつけ事件へとつながっていくので、事件の全容を解決するために二つの再会を経なければならない皮肉。
もう一人の女−新見まさ子もまた、恋によって運命を翻弄された犠牲者である。江原という老人の愛人でありながら山代と知り合って誘惑され、真摯な愛情を注ぐようになるが、山代の彼女への思いは打算でしかなかった。否、陽子のために打算をせずにはいられない状況に陥ってしまっていた。まさ子はパトロンである江原へのすまなさと山代への愛情との板ばさみになりつつ、山代を江原に紹介してセザンヌの絵画(それこそが贋作だった)を売りつける手助けをする。その代金が他の女のために使われると知ったときのまさ子の落胆ぶりは、語り聞かされた山代にとっても許容できない過去ではあるが、思い出すことすらできず、物語を聞いているような感覚でしかない。その客観性にもある種の悲しさがつきまとう。知っていくことも悲劇なら、知らずに過ごすことも悲劇、知っても感受することができないことも悲劇。しかし、過去とは何か?自分とは何か?を見つめていこうとする山代。
…記憶の全てを回復した時、山代に現われたのは、空白だった三年間の自分を悔いる姿勢と、それを支えるつかさの存在だった。新見まさ子をだまそうとしてだましきれず、あの日自殺を決意して崖の上に立った山代。息を吹き返し、記憶を呼び戻した時点で、山代の心はまさ子への恋情、陽子への盲目的な献身を呼び戻すことには至らず、それらを切り離してつかさと生きようと決心する心が芽生えていた。春の陽が落ちる交差点を二人で歩きながら交わされた二人の会話が心地よい。
「何もかも違う。記憶が戻っても、戻らなくても、同じことなんだ。−やはり、僕という人間は別の人間になったんだな」
山代が実感を籠めて言うと、
「そうなんです。わたくしにはそれがよく判ります。前の山代さんでしたら、わたくし、こうして二人で街を歩いたりする気にはならなかったと思いますわ」
井上靖氏は本作品において、格調高く、味わい深いミステリーの構築に成功したと言えよう。 (2004年7月4日)